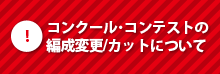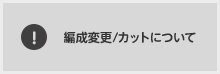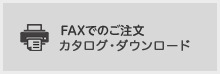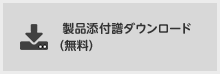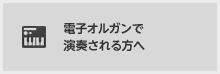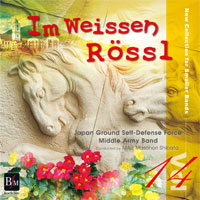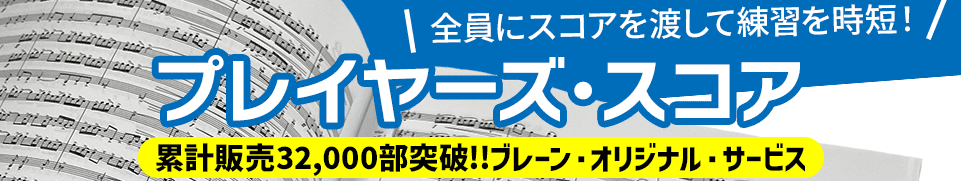
宅配スコア閲覧
時折見せる西洋風の美しい旋律が輝く!原曲は、金管八重奏の曲で、そこから極小吹奏楽の編成へ、そして、さらに進化してこの楽譜になったという片岡寛晶氏の思いが深い作品です。曲調は、片岡氏の有名作品「マカーム・・・
楽曲詳細情報
- 作曲
- 片岡寛晶(Hiroaki Kataoka)
- 演奏時間
- 8:00(約)
- グレード
- 4
- 主なソロパート
- Ob./E♭Cl./B♭Cl./B.Cl./S.Sax./A.Sax./T.Sax./Trp./Hrn./Tuba/Perc.
- Trp.最高音
- 1st:G / 2nd:Es
- 演奏最少人数
- 20人
- 編成
- 吹奏楽
楽器編成
- Piccolo
- Flute
- Oboe (opt.)
- Bassoon (opt.)
- Clarinet in E♭ (opt.)
- 1st Clarinet in B♭(div.)
- 2nd Clarinet in B♭
- Bass Clarinet in B♭
- 1st Alto Saxophone in E♭
- (doub. Soprano Saxophone in B♭)
- 2nd Alto Saxophone in E♭(opt.)
- Tenor Saxophone in B♭
- Baritone Saxophone in E♭
- 1st Trumpet in B♭
- 2nd Trumpet in B♭
- 1st Horn in F
- 2nd Horn in F
- 1st Trombone
- 2nd Trombone
- Euphonium
- Tuba
- String Bass(opt.)
- 1st Percussion
- Sizzele Cymbal
- Timpani
- Suspended Cymbal
- Bongo
- Bass Drum
- Crotale or Glockenspiel
- Ribbon Crasher or Tambourine
- 2nd Percussion
- Bass Drum
- Tam-tam
- Suspended Cymbal
- 3 Wood Blocks
- Ribbon Crasher or Tambourine
- 4 Toms
- Hi-Hat
- Chimes
- Spring Drum
- Rain Stick
- Darbukar or Djambe or Bongo
- Sleigh Bell
- 3rd Percussion
- Vibraphone
- Crotale or Glockenspiel
- Chimes
- 2 Small Gongs or 2 Suspended Cymbals
- Ratchet
- Marimba
- Glockenspiel
- Spring Drum
- Wind Chime
- Triangle
- Finger Cymbal
- Sleigh Bell
- Xylophone
- 4 Wood Blocks
- Snare Drum
- 4th Percussion(opt.)
- Sizzle Cymbal
- Chimes
- Suspended Cymbal
- Guiro
- Glockenspiel
- Triangle
- 木柾
- Crotale
- Finger Cymbal
- Whip
- Xylophone
楽曲解説
2018年、川口市・アンサンブルリベルテ吹奏楽団より委嘱のお話を頂き、金管打楽器8重奏作品を作曲、同年、埼玉県アンサンブルコンテストにおいて初演されました。
作品の更なる可能性を求め吹奏楽版に着手し、翌2019年、仙台城南高校吹奏楽部の若き力漲る13人の手により、吹奏楽版が初演されました。原曲は、8人で演奏可能なため、大きな編成にする事など容易だと私は思っていたのですが、限られた人数とメンバーの個性を活かした、オリジナリティー溢れる作品として完成させる事は、とても苦労した点であり、また面白くもありました。
極小編成ながらオーボエ奏者がいた事や、アラブ・トルコ音楽などで頻繁に用いられる、民族打楽器「ダラブッカ」が揃っていた事がきっかけで、妖艶な舞踏を彷彿とさせる旋律を加筆させ完成。その後、練習を積み重ねた城南高校は、ムードいっぱいの演奏で聞く人の心を掴み、東北代表として第19回東日本学校吹奏楽大会に初出場となりました。金沢歌劇座の黒いステージで、13人とは思えない高いパフォーマンスを目の当たりにした聴衆の割れんばかりの拍手と喝采…
心を込めて指揮をしてくださった、顧問の佐藤 学 先生の雄姿を、私は一生忘れません。
ペルシア音階を用いた旋律は、中東音楽独特の雰囲気が漂い、時に現代的で土俗的、そして舞曲的な一面があります。今作品は13人版を基に、2管編成としてオーケストレーションを見直しました。表現・歌い方・躍動・ウネリなどに工夫をし、曲を通じてバンドの持ち味が活きるよう取り組んで頂ければ幸いです。最後になりますが、吹奏楽の新たな可能性を模索し完成させた「ムジカ・アーヴァーズ」が、皆さまに長く愛され続けますことを心より願っております。
(片岡寛晶)