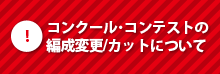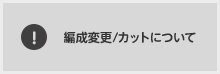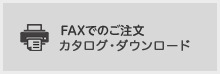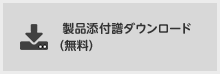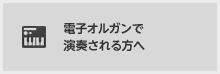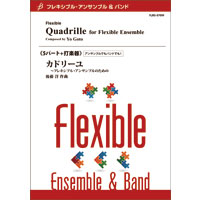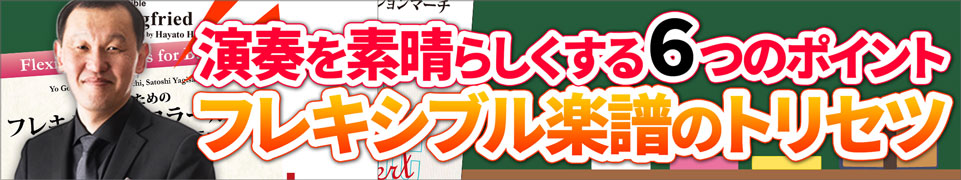
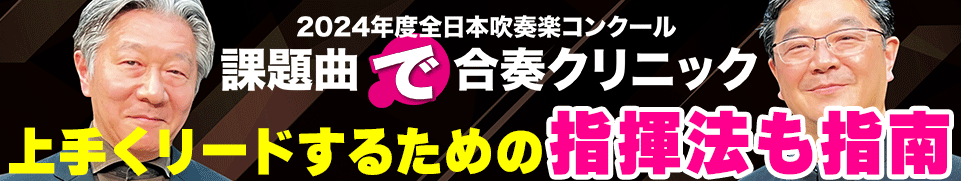
室内楽での演奏も非常に相性がいいエレガントな雰囲気の楽曲!美しく軽やかにどうぞ!
♪詳細情報♪
▼楽器編成▼
Part 1
Flute
Oboe
Clarinet in E♭
Clarinet in B♭
Soprano Saxophone in B♭
Alto Saxophone in E♭
Trumpet in B♭
Oboe
Clarinet in E♭
Clarinet in B♭
Soprano Saxophone in B♭
Alto Saxophone in E♭
Trumpet in B♭
Part 2
Flute
Oboe
Clarinet in B♭
Alto Saxophone in E♭
Trumpet in B♭
Oboe
Clarinet in B♭
Alto Saxophone in E♭
Trumpet in B♭
Part 3
Clarinet in B♭
Tenor Saxophone in B♭
Horn in F
Tenor Saxophone in B♭
Horn in F
Part 4
Bassoon
Tenor Saxophone in B♭
Horn in F
Trombone
Euphonium
Tenor Saxophone in B♭
Horn in F
Trombone
Euphonium
Part 5
Bassoon
Bass Clarinet in B♭
Baritone Saxophone in E♭
Trombone
Euphonium
Tuba
String Bass
Bass Clarinet in B♭
Baritone Saxophone in E♭
Trombone
Euphonium
Tuba
String Bass
Percussion
Snare Drum
Suspended Cymbal
Triangle
Glockenspiel
Vibraphone
Suspended Cymbal
Triangle
Glockenspiel
Vibraphone
♪楽曲解説♪
オリジナルは吹奏楽のための作品で、1982年に全日本吹奏楽連盟の委嘱により作曲。翌’83年の全日本吹奏楽コンクール課題曲のひとつとなりました。40年近く前のことで、当時私は20代の半ば。自分にとっては、作曲家としてのキャリアの出発点となった重要な作品です。
曲名は、18世紀にフランスで起こったとされる舞曲の名称です。エレガントな舞曲風の音楽として構想したこと、そして4組のカップルが四角になって踊るため「4」を意味するquadriという接頭辞が付けられているその名称が、各部分が4度跳躍の動機によって始まるこの作品にふさわしいと考えましたが、音楽の様式的な面においては特に深い関係はありません。
もともとパワーを誇示したり、華やかな演奏効果を狙ったりはしていないため、少人数での演奏にも適した作品です。しかしフレキシブル・アンサンブルのためのこの編曲では、5つのパートと打楽器で演奏可能とするため、本来7や9の和音を用いている部分では和音の組立てをオリジナルと変更したところもあります。また、響きの色彩を創ること、さらにその色彩を変化させていくことが表現の重要なポイントであり、そのためにはまずその色彩を、変化を感じ取ること、そしてその変化を各パート間の音量的/音色的バランスよって表すことが音楽的な課題となるでしょう。人数に余裕があるグループの場合、複数のパートを兼務する奏者をつくり、その役割の移動によってバランスや色彩の変化を演出しても面白いと思います。
(後藤 洋)